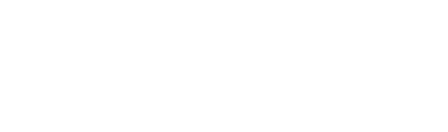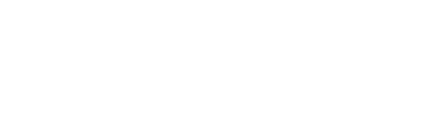お知らせ・イベント・コラム

住宅ローンの長期固定金利が上昇したら、変動金利も上昇するのか
最近、住宅ローンの長期固定金利が上昇したことを受けて、変動金利も上昇するという記述が、インターネットなどで散見されます。
確かに、景気が回復したアメリカではそのような流れになっていますが、今回の長期固定金利の上昇は日銀の政策変更という点に注意する必要があります。
今回は、両者の違いを区別し、日本の住宅ローン金利動向を解説します。

景気が回復したアメリカでは住宅ローン金利が上昇
まず、住宅ローン金利がどのように上昇していくのかを解説します。
住宅ローン金利は、10年物国債の利回りである長期金利に連動する長期固定金利と、銀行間の取引である無担保コール翌日物金利が代表的な、短期金利に連動する変動金利があります。
そして、現在の発達した金融システムでは、国債を取引する債券市場において、将来的に景気が回復する見通しが強まった場合、市場参加者は国債を売って、より儲かる株式を買う行動に出ます。
国債が売られると、当然ながら国債の値段は下がりますので、国債の売買で利益を狙っていた市場参加者からも損失確定の売りが続き、国債の値段は下落、相対的に利回りは高くなり、長期金利も上昇します。
さらに、景気が回復するとインフレ(物価上昇)が起きますので、長期金利に続いて短期金利も上昇します。
通常はこのような流れにより、まず長期金利に連動する長期固定金利が上昇した後、短期金利に連動する変動金利も上昇するのです。
アメリカではリーマンショック後、景気が急速に落ち込んだため、通貨供給量を増やす量的緩和策を9年間実施しましたが、景気が回復しインフレの兆候も出てきたため、利上げに踏み切りました。
これにより、アメリカの長期金利が上昇したため、長期固定金利も上昇。
また、アメリカでは特にインフレがひどく、利上げが複数回行われたため、短期金利も長期金利並みに上昇、変動金利も上昇しました。
参考までに、アメリカの長期金利は3%台で推移していますが、住宅ローンの長期固定金利は4~5%程度まで上昇しています。
日本の長期固定金利上昇は、あくまで日銀の政策変更
日本の金融政策をつかさどる日銀も、アメリカのような景気回復のシナリオを描いていたのですが、6年目に入る金融緩和は成果を上げていません。
特に日銀が実施したマイナス金利政策は、短期金利も長期金利も限りなく低く抑えることで、銀行が企業への融資を活発に行い、景気を回復させるもくろみでした。
しかし現実には、銀行が国債を大量に購入したため、国債の値段が急騰、相対的に利回り換算すると、利回りがマイナスになる異常な事態を招きました。
これにより、銀行は国債からの配当が実質的に帳消しになるとともに、融資金利と預金金利が逆転してしまう逆ザヤも発生、地銀を中心に金融機関収益は大きく悪化しました。
金融緩和を進めすぎて、以前の日本の金融危機のような事態になったら、元も子もありません。
そこで、日銀は国債からの配当が減っている金融機関収益に配慮し、長期金利の上昇幅を0.1%程度から0.2%程度まで上昇することを容認したのです。
この政策変更後、国債からの配当を期待した市場参加者が国債売り(利回りは上昇)に走り、長期金利は日銀の思惑通り、0.1%程度で推移しています。
そして、長期金利が0.1%程度まで上昇するということは、長期金利に連動する長期固定金利も当然ながら上昇します。
この動きが7~9月に起きた、長期固定金利の上昇です。
しかし、今回の長期金利の上昇は、あくまで金融機関収益に気を配った、日銀の政策変更が原因です。
日銀の金融政策決定会合では、現在も短期金利はマイナスを維持すると書かれているため、短期金利は上昇せず、変動金利も上昇することはないのです。
そして、短期金利の上昇要因になりやすいインフレも、日本ではその気配すらありません。
日本では、デフレマインドが強すぎるのが原因ですが、なかなか解消できていないのが現実です。
従って、日本がアメリカのような景気回復とインフレの状態になるには、まだ相当の時間がかかる見込みです。
金融緩和の副作用が目立つ現在、日銀には新たな対策が求められそうです。
Works
お問い合わせ・
モデルハウス見学の
ご予約はこちら
お電話でのご相談・ご予約
TEL 0120-411-185
営業時間 10:00-18:00 (水曜・木曜定休)
Webフォーム