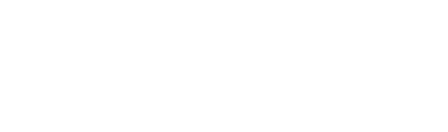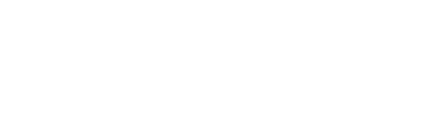お知らせ・イベント・コラム

住宅ローンの流れを、マンションと注文住宅で比較してみる
実際に住宅を購入した場合の住宅ローンの流れはどうなるのでしょうか。マンション購入の場合と注文住宅で自宅を建築する場合ではその流れが大きく異なりますので、具体的に別々に紹介していきます。

マンション購入の場合
マンションなどの大規模物件では、購入者1人1人に個別に対応することが出来ません。そこで、お金を借りる契約である「金銭消費貸借抵当権設定契約(金消)」を1度にまとめて行い、事務負担の軽減を計っています。
具体的には、上記の契約や火災保険の契約など、必要な契約に関する銀行や保険会社の担当者が集まり、購入者は流れ作業のような感じで順番に回っていきます。
従って、住宅ローンの選択肢に関しても販売会社が提携している銀行の住宅ローンに限られ、購入者が自由に住宅ローンを選択することは原則として出来ません。
効率的と言えば効率的ですが、実際に入居するまではマイホームを購入したという実感が、わきにくいという欠点もあります。
注文住宅で家を建てる場合
自由設計・注文住宅の場合は、綿密に打ち合わせが必要ですのでマイホームが完成していくのを実感できますが、資金面では何回かに別けて資金が必要なため注意が必要です。
通常の工務店の資金フローとしては、土地を購入する場合はその時、そして自宅建築の時には着工時に30%、上棟時に40%、完成時に30%の資金を支払う必要があります。
この場合、土地が3,000万円と建物が2,000万円の総額5,000万円だとしても、銀行側がその都度資金を出してくれなければ、工務店側でも工事が進みません。
そこである程度を自己資金でまかなえない場合は、柔軟な融資に応じてくれる銀行を探すことが、金利水準よりも先の検討事項になります。
ただ、銀行側も自宅を建築する場合において上記のような商慣行があることは承知しており、ネット銀行などを除けば、特段神経質になることはありません。
実際の資金フローの流れ
ここでは、メガバンクの中でも柔軟に対応してくれる三井住友銀行の例で見ていきましょう。
三井住友銀行では土地を先行して購入する際に、建物の見積もり書・プラン図なども添付してもらい、その時点で全体の融資を行うかの判断をします。
ここで問題がなければ、まず土地購入に必要な資金を融資します。ちなみに銀行側の債権保全上の措置である「抵当権」は保証会社を抵当権者として、土地代だけの債権額3,000万円を1番で打ちます。
(抵当権とは不動産登記の1つで、万が一、債務者(借入者)が住宅ローンを返済出来ない時に、最終手段として銀行側が自宅を競売して資金を回収するための権利です)
次に、工務店に支払う3回の資金は「金銭消費貸借契約(金消)」で3回の分割実行であることを明記し、それぞれの時期に必要な資金を融資します。
なお、債権保全上の観点から建物の着工時に30%を融資した時点で、建物の総額である債権額2,000万円の抵当権を2番で打ちます。
そして、建物が完成した時に建物にも抵当権を追加設定し、土地代の債権額3,000万円を1番、建物の債権額2,000万円を2番で打つことで土地と建物の共同担保となり、銀行側としても債権保全上は問題ありません。
最初に資金フローを見ると、随分ややこしそうに感じますが、実際にこれらの抵当権の登記は司法書士が行うため、建築主がそこまで難しく感じる必要はありません。
ただし、分割実行の場合は融資ごとに抵当権を打つ銀行もあり、通常よりも司法書士報酬が膨らみ、登記費用全体が高くなる懸念があります。
また、当初から土地代金と建物代金の合計で1本とみなし、その都度融資してくれる銀行もあるなど、銀行により融資形態は異なります。
まとめ
自宅を建築する場合は、まず使い勝手の良い銀行を探すことが何よりも大切です。金利が気になるのもわかりますが、そればかり気にしていると必要なときに必要な資金が出ない恐れがあります。
マンション購入と注文住宅で一から家づくりをする場合では、銀行の選び方が違う点を抑えて頂ければと思います。
ホロスホームでは第三者の立場からお客様にふさわしい金融機関のご紹介もいたしますので、お気軽にご相談下さい。
Works
お問い合わせ・
モデルハウス見学の
ご予約はこちら
お電話でのご相談・ご予約
TEL 0120-411-185
営業時間 10:00-18:00 (水曜・木曜定休)
Webフォーム